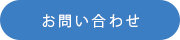2023.05.27
長野の猟銃事件から猟銃の保管について

長野県中野市江部で25日夕に発生した猟銃発砲・立てこもり事件
犠牲者は警察官2人を含む計4人。日本の、しかも長閑な田畑が広がる地域で、まさかの事件です。
容疑者は報道で知られているように、同市議会議長の長男で同市江部、農業,青木政憲容疑者(31)という。
その動機は、「死亡した一般人女性2人について「悪口を言われていると思い、殺してやろうと考えた」と供述しており、県警は一方的に恨みを募らせた末、凶器を準備し、計画的に2人を狙った疑い」といいます。
凶器は〝サバイバルナイフのような刃物〟と、青木容疑者は猟銃の所持免許を持っていて、報道によれば4丁を所有していたという、一般人の感覚からすれば驚くような話です。
銃所持の問題点
まず、日本では〝猟〟を行う事を目的に、所定の試験や研修を経て認められるらしく、報道によれば、その免許を持っている人が約17万人もいるらしいのです。
もちろん、しっかりと管理をして青木容疑者のような人はいないとは思いますが、この青木容疑者が兇行に及ぶ前は、青木容疑者もその〝しっかりと管理をし‥〟の中の一人であったわけです。
そう考えると、その17万人の中に、再び同じような事件を起こす人が出てくるかもしれない、と思ってしまうのは普通の心理ではないでしょうか。
猟銃の管理方法の見直しや、その他の対処方法を改めて考える必要があるのではないのでしょうか。
猟銃の免許は、必ずしも本当に猟に出る人でなくても持っている場合があります。それも、(猟)銃を常時持っているという事です。考えると恐ろしくなります。
もし、あなたの家の隣に住んでいる人が、自宅で銃を所持していると知ったら、何となく不安な気持ちになるはずです。
どんな人物か分かりませんし、何かの事で近隣トラブルになって口論に発展したら、逆上して銃を発砲するのではないか?などと思っても不思議ではありません。何故なら、実際に今回のような事件があるからです。
大日本猟友会「鉄砲所持許可」によれば銃の保管方法について、次のように記載されています。
〝許可を受けた銃砲の自宅保管には専用の「ガンロッカー」が必要です。これとは別に、実包の自宅保管用には「装弾ロッカー」も必要です。〟
つまり、自宅で銃も玉も置いておけるという事であり、その管理は自己責任という事なのです。
まさに、ここに大きな問題があると思うのです。
では、どのような管理が必要か?というと、これはあくまでも私見ですが、
⑴銃の保管場所‥‥銃砲店、警察署、または交番、派出所
⑵装弾の保管場所‥銃砲店
⑶猟に行く申告‥‥銃の保管場所から受け取る際と、装弾を受け取る場合、猟に行く場所や日時などを書面で申告させる
特に、⑶は重要です。そもそも護身ではなく狩猟が目的な免許なわけですから、猟も目的もないのにも関わらず、銃や装弾を持っている必要はないわけです。
この3点を行うだけで、猟銃による凶行はなくなると思うのです。
では、何故こういう事をしないのか?保管管理の大変さだとか、緊急時の使用(突発的な害獣駆除)があるのかも知れませんが、人の命を失う重大さを考えれば、これを〝難しいからやらない〟という事が果たして言えるでしょうか。
また、⑴〜⑶が絶対にできないのならば、この銃所持者を定期的な監視調査をするべきで、「最近の挙動におかしな点はないか?」や、「何かトラブルを抱えていないか?」、「交友関係に変化はないか?」などを調べて公安委員会に報告書を提出するという‥‥こういう事ができるのは、民間の調査会社です。
探偵業法(探偵業の業務適正化に関する法律)が成立し、施行された時、平沢代議士が「犯罪未然防止産業として‥‥」と、業界団体が行う業法成立の祝賀パーティーで言い放った言葉で、よく記憶しています。
犠牲者は警察官2人を含む計4人。日本の、しかも長閑な田畑が広がる地域で、まさかの事件です。
容疑者は報道で知られているように、同市議会議長の長男で同市江部、農業,青木政憲容疑者(31)という。
その動機は、「死亡した一般人女性2人について「悪口を言われていると思い、殺してやろうと考えた」と供述しており、県警は一方的に恨みを募らせた末、凶器を準備し、計画的に2人を狙った疑い」といいます。
凶器は〝サバイバルナイフのような刃物〟と、青木容疑者は猟銃の所持免許を持っていて、報道によれば4丁を所有していたという、一般人の感覚からすれば驚くような話です。
銃所持の問題点
まず、日本では〝猟〟を行う事を目的に、所定の試験や研修を経て認められるらしく、報道によれば、その免許を持っている人が約17万人もいるらしいのです。
もちろん、しっかりと管理をして青木容疑者のような人はいないとは思いますが、この青木容疑者が兇行に及ぶ前は、青木容疑者もその〝しっかりと管理をし‥〟の中の一人であったわけです。
そう考えると、その17万人の中に、再び同じような事件を起こす人が出てくるかもしれない、と思ってしまうのは普通の心理ではないでしょうか。
猟銃の管理方法の見直しや、その他の対処方法を改めて考える必要があるのではないのでしょうか。
猟銃の免許は、必ずしも本当に猟に出る人でなくても持っている場合があります。それも、(猟)銃を常時持っているという事です。考えると恐ろしくなります。
もし、あなたの家の隣に住んでいる人が、自宅で銃を所持していると知ったら、何となく不安な気持ちになるはずです。
どんな人物か分かりませんし、何かの事で近隣トラブルになって口論に発展したら、逆上して銃を発砲するのではないか?などと思っても不思議ではありません。何故なら、実際に今回のような事件があるからです。
大日本猟友会「鉄砲所持許可」によれば銃の保管方法について、次のように記載されています。
〝許可を受けた銃砲の自宅保管には専用の「ガンロッカー」が必要です。これとは別に、実包の自宅保管用には「装弾ロッカー」も必要です。〟
つまり、自宅で銃も玉も置いておけるという事であり、その管理は自己責任という事なのです。
まさに、ここに大きな問題があると思うのです。
では、どのような管理が必要か?というと、これはあくまでも私見ですが、
⑴銃の保管場所‥‥銃砲店、警察署、または交番、派出所
⑵装弾の保管場所‥銃砲店
⑶猟に行く申告‥‥銃の保管場所から受け取る際と、装弾を受け取る場合、猟に行く場所や日時などを書面で申告させる
特に、⑶は重要です。そもそも護身ではなく狩猟が目的な免許なわけですから、猟も目的もないのにも関わらず、銃や装弾を持っている必要はないわけです。
この3点を行うだけで、猟銃による凶行はなくなると思うのです。
では、何故こういう事をしないのか?保管管理の大変さだとか、緊急時の使用(突発的な害獣駆除)があるのかも知れませんが、人の命を失う重大さを考えれば、これを〝難しいからやらない〟という事が果たして言えるでしょうか。
また、⑴〜⑶が絶対にできないのならば、この銃所持者を定期的な監視調査をするべきで、「最近の挙動におかしな点はないか?」や、「何かトラブルを抱えていないか?」、「交友関係に変化はないか?」などを調べて公安委員会に報告書を提出するという‥‥こういう事ができるのは、民間の調査会社です。
探偵業法(探偵業の業務適正化に関する法律)が成立し、施行された時、平沢代議士が「犯罪未然防止産業として‥‥」と、業界団体が行う業法成立の祝賀パーティーで言い放った言葉で、よく記憶しています。