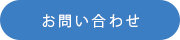2023.06.01
人物の〝行動〟という極めて重要な情報

人物に関する情報とは
人物に関する情報を得る方法は幾つかあります。
例えば〝公簿〟(住民票や戸籍、商業謄本や不動産謄本など)でも、様々な事柄を読み取る事ができます。
また、相談者が既に知り得る情報やSNSの内容も、その人物に関わる重要な情報です。
さらに調査会社は、これらから読み取った情報を元に、データ検索や取材、内偵などで独自に新たな情報を得ていきます。
そうやって、その人物に関する事柄を浮き彫りにしていくのです。
ただ、これらの情報は必ずしもリアルタイム(現状)の情報であるのか保証はできません。
住民票は債権者など利害関係のある人や正当な事由があって、弁護士が照会をかけるなどしないと取得できません。戸籍や戸籍の附票なども同様です。
不動産登記簿や商業登記簿は誰でも取得する事ができます。そのいずれからも様々な情報を得る事ができますし、内容如何でその人物に関係する事柄から、次の調査段階に進むヒントも得る事ができます。
問題は、そこに記載されている事が必ずしも現在の内容であるとは限らない事です。
もちろん、過去の情報であっても、その過去の情報が大変大きな情報になり得るので無駄ではありません。
住民票でも同じで、仮に転出届けが出ていて住民票に異動先が記載されていても、それは〝予定先〟であって、本人が転入先に届けを出さないと転居先の住所は分からなかったりします。
つまり、転出届出で申告した転居先と、実際に転居した先が違っても、転入先に転入届けを出せば良いわけで、その転入届けを出さない人もいるので、こういう場合にはそこ(申請先で取得した住民票)に記載された転居予定先は意味がないのです。
商業登記簿には、代表取締役の住所が記載されていますが、これも必ずしも現在もそこに住んでいるとは限りません。
取材や内偵も、新たな情報ではあるものの、噂や人伝ての情報になりますから、これもどこまで信憑性があるのかは保証はないのです。例えば、その人物について近隣に取材したとしても、その人の話というのは、その人の主観的な話であったり、あるいは自分が知っているかのように話しても、実はそれも人伝てだったりする事もあります。また人伝ての話から誇張されて伝わった話を聞いた内容であったりもしますし、その人の性格によっては適当に答える人もいます。
但し、取材や内偵はその前に得た事前の情報や複数の人から聴取する事で、整合性がとれるものなのかを分析しますから、ある程度、正しい情報には近いものにはなります。
いずれにしても、人物に係る〝現在の情報〟なの?かと問われれば、確かに〝リアルタイム〟ではないという事になります。
人物の「行動」という確かな情報
リアルタイムな情報を得るためには、どうしても現在の〝行動〟から得る方法しかありません。
つまり、行動確認の事です。
行動確認で得れる情報とは、特定人物の生活に係わる事柄です。一日の始まりから、何処に行き、誰と会い、何をしているのか。これらの情報から、その人物の生活パターンや交友関係、お金の使い道、趣味、異性関係、嗜好性、性格、二面性などが垣間見れて、これら全ての事からその人物の人間性までもが窺い知れるのです。
警察では、これを〝行確(コウカク)〟と言っており、犯罪者を逮捕する前に、予めその人物がいる場所や時間帯などを把握したりする事でも行うようです。もちろん張込みも行います。張込みなどは交番勤務の警察官でも、私服に着替えてコンビニなどで〝ひったくり犯〟などを捕まえるために張り込んでいる警官もいるようで、実際に会った事もあるくらいです。
これらは、聞き込みや過去の情報だけで犯人を捕まえる事はできないため、どうしてもリアルタイムな情報を得る手段として〝コウカク〟に頼るのです。
個人の相談などでも同じです。浮気などは、メールやLINEなどから浮気の疑いは間違いないけれど、確かなリアルタイムな証拠がないため、裁判になれば証拠能力としては少し弱いという事で、行動確認からリアルタイムな浮気の確かな証拠を得るために行うわけです。
これと同じように企業においても「何某が不正を働いている」、「どうも経理の女性と何某が不倫関係にあると噂がある」、「何某が取引先と業務以外で頻繁に会っているという噂がある」、「何某が会社を辞めようとしているが、どうも同業に転職するようだ」など、〝火のないところに煙は〟…と言われるように、これらの情報はほとんど事実に相違ない事があります。
それでも、あくまでも噂や人伝てに聞いた事柄なので、これを以てその何某に〝横領〟や〝背任〟の嫌疑をかけるわけにもいかないのです。
情報漏洩のブログでも触れたように、実際に問題が発覚してからでは、その人物を法に訴えたり解雇しても、会社が失った社会的信用や、被った損害は決して消す事はできないのです。
そのために、〝疑いの域〟である時点で〝リアルタイム〟な情報から、〝その事実関係を知る事〟が、行動確認調査の最も有効な活用方法なわけです。
それでも、「まだ何も起きていないのに、これだけの費用をかけるのはどうか…」とか、中には「事実そうだと決まったわけでもないのだから…少し様子をみよう」という人もいます。
おおよそ、こういう人に限って問題が表面化してから慌てて調査依頼をしたりするのです。
そうして問題が表面化した時に、記者会見などで必ず口にするのは、〝寝耳に水〟という事です。
〝噂〟や〝人伝て〟の話であっても、それがもしも事実であったとすれば、将来問題にされるかも知れない事態は想定できた事に対して、〝何もしなかった〟という事になってしまいます。
そうして、問題が表面化してから、第三者委員会などを立ち上げ、内部調査などを行い、「やる事はやりました」という形式だけの事をするだけです。
例えるなら、病気なってから生命保険に入ろうとか、怪我をしてから傷害保険に入ろうなどと言うようなものなのです。
人間は常に病気や怪我をする可能性と隣り合わせなわけで、治療費のリスクだけでなく、その後の生活にかかるリスクはどうしても避けなくてはなりません。
初めて生命保険という仕組みができた時、その営業マンが、お客様に「眼の中に入れても痛くない可愛い我が子が、病気になるとか死んだらお金が貰えるなんて、お前は悪魔か!」などと言われたそうです。
しかし、現代ではそのリスクを避けようとする生命保険や損害保険は当たり前の事になっています。
問題が生じる前に、その可能性を想定してリスクを避ける事の大切さは企業にとっても同じ事なのです。
特に企業が不祥事などで受ける損害額は計り知れないものがあり、民事責任については損害賠償額が数百億円に及ぶ場合もあると言われています。
顧客の情報流出、会計不正、商品やサービス品質不良・データ偽装や改ざんなどの企業不祥事が相次いでいる事は周知の事ですが、当該企業の信用が失墜することで、補償金や賠償金等の経済的損失にとどまらず、企業の存続さえも危ぶまれる甚大なダメージを受ける例も数多く見られます。
これら全ては〝ヒト〟という企業の三大資産の〝ひとつ〟から派生する事が最も多いため、その人物を知る上で〝行動という情報〟は極めて重要なのです。
人物に関する情報を得る方法は幾つかあります。
例えば〝公簿〟(住民票や戸籍、商業謄本や不動産謄本など)でも、様々な事柄を読み取る事ができます。
また、相談者が既に知り得る情報やSNSの内容も、その人物に関わる重要な情報です。
さらに調査会社は、これらから読み取った情報を元に、データ検索や取材、内偵などで独自に新たな情報を得ていきます。
そうやって、その人物に関する事柄を浮き彫りにしていくのです。
ただ、これらの情報は必ずしもリアルタイム(現状)の情報であるのか保証はできません。
住民票は債権者など利害関係のある人や正当な事由があって、弁護士が照会をかけるなどしないと取得できません。戸籍や戸籍の附票なども同様です。
不動産登記簿や商業登記簿は誰でも取得する事ができます。そのいずれからも様々な情報を得る事ができますし、内容如何でその人物に関係する事柄から、次の調査段階に進むヒントも得る事ができます。
問題は、そこに記載されている事が必ずしも現在の内容であるとは限らない事です。
もちろん、過去の情報であっても、その過去の情報が大変大きな情報になり得るので無駄ではありません。
住民票でも同じで、仮に転出届けが出ていて住民票に異動先が記載されていても、それは〝予定先〟であって、本人が転入先に届けを出さないと転居先の住所は分からなかったりします。
つまり、転出届出で申告した転居先と、実際に転居した先が違っても、転入先に転入届けを出せば良いわけで、その転入届けを出さない人もいるので、こういう場合にはそこ(申請先で取得した住民票)に記載された転居予定先は意味がないのです。
商業登記簿には、代表取締役の住所が記載されていますが、これも必ずしも現在もそこに住んでいるとは限りません。
取材や内偵も、新たな情報ではあるものの、噂や人伝ての情報になりますから、これもどこまで信憑性があるのかは保証はないのです。例えば、その人物について近隣に取材したとしても、その人の話というのは、その人の主観的な話であったり、あるいは自分が知っているかのように話しても、実はそれも人伝てだったりする事もあります。また人伝ての話から誇張されて伝わった話を聞いた内容であったりもしますし、その人の性格によっては適当に答える人もいます。
但し、取材や内偵はその前に得た事前の情報や複数の人から聴取する事で、整合性がとれるものなのかを分析しますから、ある程度、正しい情報には近いものにはなります。
いずれにしても、人物に係る〝現在の情報〟なの?かと問われれば、確かに〝リアルタイム〟ではないという事になります。
人物の「行動」という確かな情報
リアルタイムな情報を得るためには、どうしても現在の〝行動〟から得る方法しかありません。
つまり、行動確認の事です。
行動確認で得れる情報とは、特定人物の生活に係わる事柄です。一日の始まりから、何処に行き、誰と会い、何をしているのか。これらの情報から、その人物の生活パターンや交友関係、お金の使い道、趣味、異性関係、嗜好性、性格、二面性などが垣間見れて、これら全ての事からその人物の人間性までもが窺い知れるのです。
警察では、これを〝行確(コウカク)〟と言っており、犯罪者を逮捕する前に、予めその人物がいる場所や時間帯などを把握したりする事でも行うようです。もちろん張込みも行います。張込みなどは交番勤務の警察官でも、私服に着替えてコンビニなどで〝ひったくり犯〟などを捕まえるために張り込んでいる警官もいるようで、実際に会った事もあるくらいです。
これらは、聞き込みや過去の情報だけで犯人を捕まえる事はできないため、どうしてもリアルタイムな情報を得る手段として〝コウカク〟に頼るのです。
個人の相談などでも同じです。浮気などは、メールやLINEなどから浮気の疑いは間違いないけれど、確かなリアルタイムな証拠がないため、裁判になれば証拠能力としては少し弱いという事で、行動確認からリアルタイムな浮気の確かな証拠を得るために行うわけです。
これと同じように企業においても「何某が不正を働いている」、「どうも経理の女性と何某が不倫関係にあると噂がある」、「何某が取引先と業務以外で頻繁に会っているという噂がある」、「何某が会社を辞めようとしているが、どうも同業に転職するようだ」など、〝火のないところに煙は〟…と言われるように、これらの情報はほとんど事実に相違ない事があります。
それでも、あくまでも噂や人伝てに聞いた事柄なので、これを以てその何某に〝横領〟や〝背任〟の嫌疑をかけるわけにもいかないのです。
情報漏洩のブログでも触れたように、実際に問題が発覚してからでは、その人物を法に訴えたり解雇しても、会社が失った社会的信用や、被った損害は決して消す事はできないのです。
そのために、〝疑いの域〟である時点で〝リアルタイム〟な情報から、〝その事実関係を知る事〟が、行動確認調査の最も有効な活用方法なわけです。
それでも、「まだ何も起きていないのに、これだけの費用をかけるのはどうか…」とか、中には「事実そうだと決まったわけでもないのだから…少し様子をみよう」という人もいます。
おおよそ、こういう人に限って問題が表面化してから慌てて調査依頼をしたりするのです。
そうして問題が表面化した時に、記者会見などで必ず口にするのは、〝寝耳に水〟という事です。
〝噂〟や〝人伝て〟の話であっても、それがもしも事実であったとすれば、将来問題にされるかも知れない事態は想定できた事に対して、〝何もしなかった〟という事になってしまいます。
そうして、問題が表面化してから、第三者委員会などを立ち上げ、内部調査などを行い、「やる事はやりました」という形式だけの事をするだけです。
例えるなら、病気なってから生命保険に入ろうとか、怪我をしてから傷害保険に入ろうなどと言うようなものなのです。
人間は常に病気や怪我をする可能性と隣り合わせなわけで、治療費のリスクだけでなく、その後の生活にかかるリスクはどうしても避けなくてはなりません。
初めて生命保険という仕組みができた時、その営業マンが、お客様に「眼の中に入れても痛くない可愛い我が子が、病気になるとか死んだらお金が貰えるなんて、お前は悪魔か!」などと言われたそうです。
しかし、現代ではそのリスクを避けようとする生命保険や損害保険は当たり前の事になっています。
問題が生じる前に、その可能性を想定してリスクを避ける事の大切さは企業にとっても同じ事なのです。
特に企業が不祥事などで受ける損害額は計り知れないものがあり、民事責任については損害賠償額が数百億円に及ぶ場合もあると言われています。
顧客の情報流出、会計不正、商品やサービス品質不良・データ偽装や改ざんなどの企業不祥事が相次いでいる事は周知の事ですが、当該企業の信用が失墜することで、補償金や賠償金等の経済的損失にとどまらず、企業の存続さえも危ぶまれる甚大なダメージを受ける例も数多く見られます。
これら全ては〝ヒト〟という企業の三大資産の〝ひとつ〟から派生する事が最も多いため、その人物を知る上で〝行動という情報〟は極めて重要なのです。